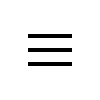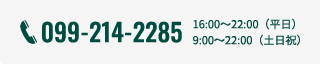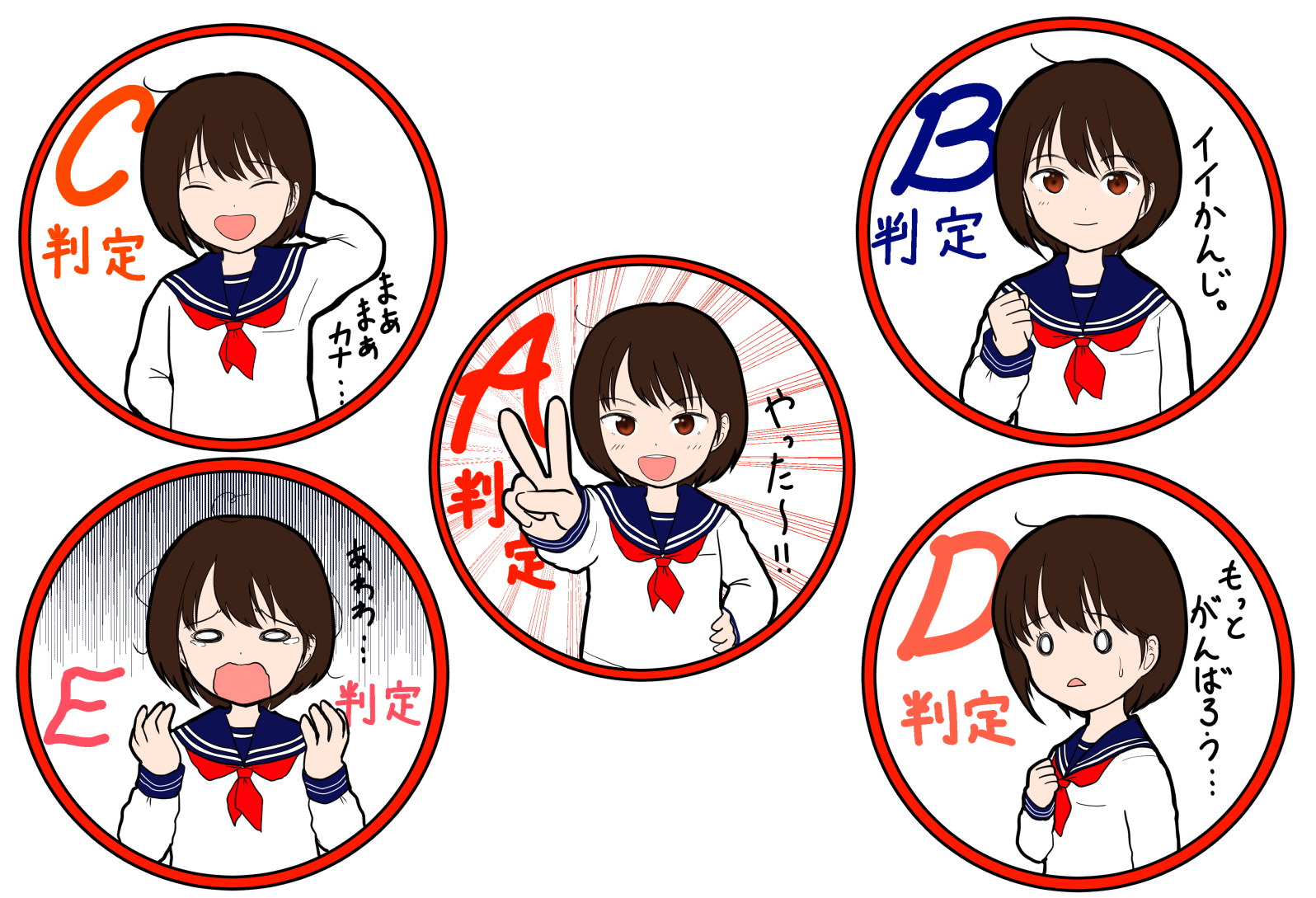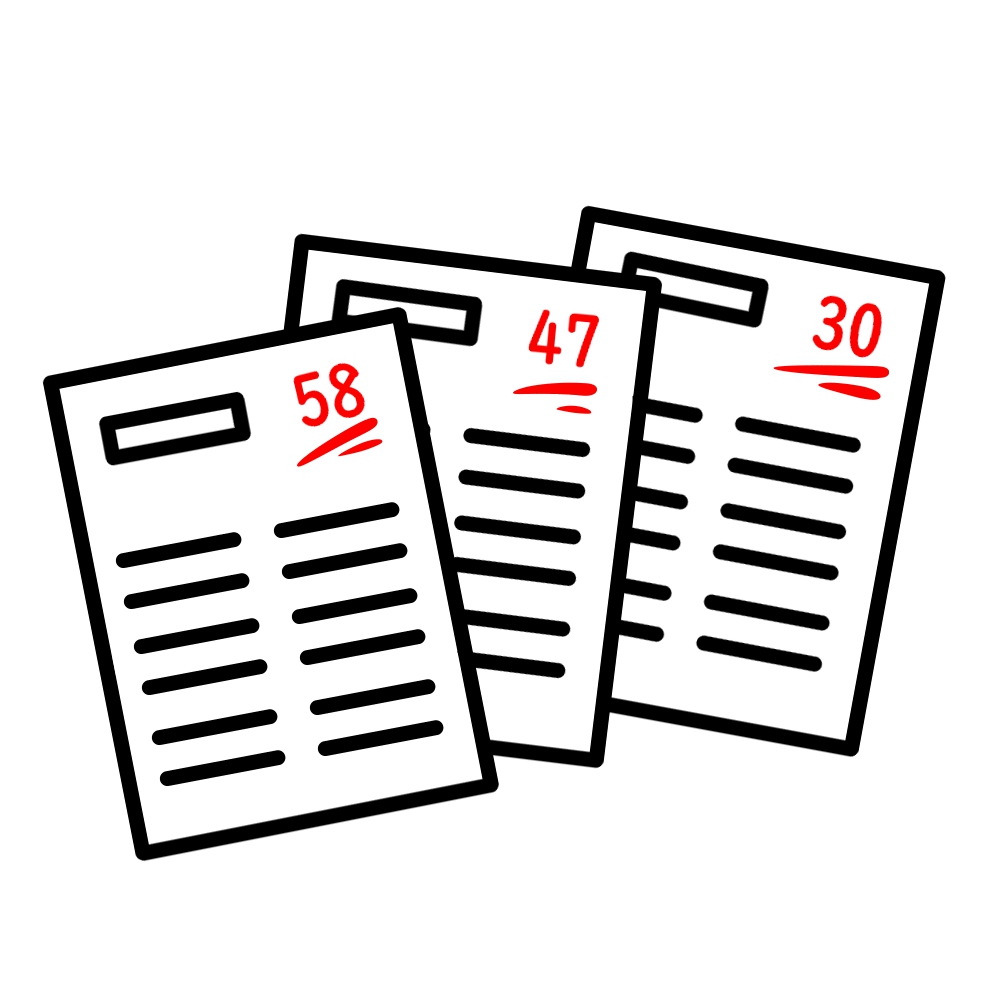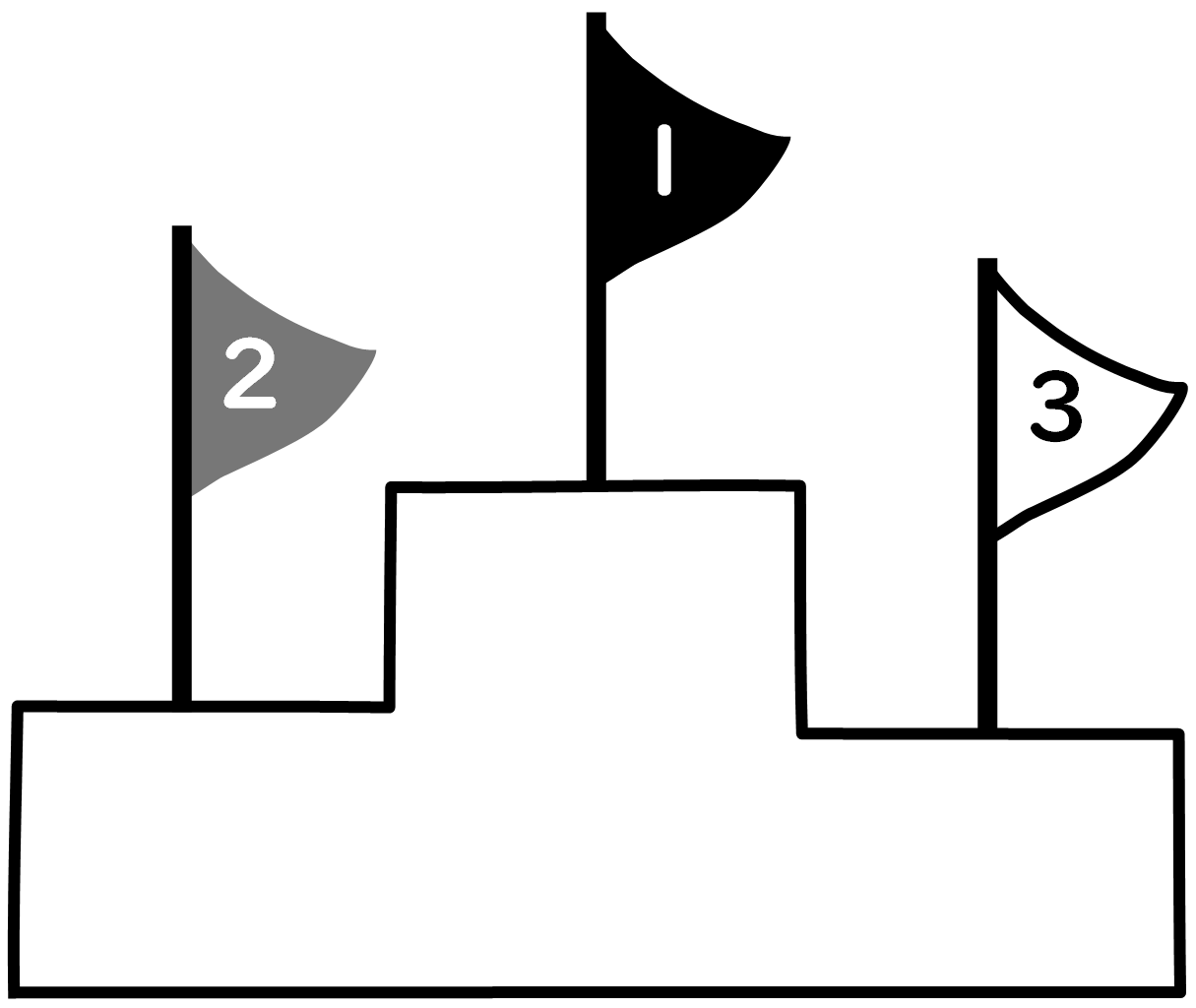全九州模試の結果判明時に確認してほしいこと
こんにちは。郷中塾の藤井です。
春休みも終わり、新学年が始まりましたね!
2年生は後輩ができ、3年生はいよいよ受験学年になりました。
新しいクラスのメンバーや担任の先生についての話に盛り上がっている時期だとは思いますが、

きちんと直視してますか?



数々のブーイングが聞こえてきますが、思うように成績が上がっていないという皆さんに向けて、2つのチェックをお願いしたいと思います!
判定よりも先に見るべきものがある






これは、受験相談に来られる生徒さんとのやり取りの中で一番多いパターンです。
このような生徒さんに、

と尋ねると、

考えたこともなかったです…

というような答えが返ってきます。
このような心構えで模試を受験しているのであれば、模試の効果は半減してしまうでしょう。
模試を受ける本来の目的は、「現状の自分の学力を把握するため」と「現在の自分の相対的な立ち位置を明確に認識するため」の大きく2点です。
1.現状の学力を把握しよう
「現状の学力を把握する」ためにはどうすればよいのでしょうか。
それは、以下の2つの手順で行うことができます。
①自分の得意・不得意を詳細に認識する。
②自分の間違いのパターンを分析する。
①については、全九州模試の成績表を見れば一目瞭然です。
「正答率が高いのに自分が間違っているという設問が多い分野」が不得意分野であり、「正答率が低いのに自分が正解しているという設問が多い分野」は得意分野と判断できます。
そうして大まかに得意・不得意分野を把握したら、次は個別の設問内容を見ていきましょう。
同じ『×』でも、
・問題の意味が分からなかった。
・問題の意味を取り違えてしまった。
・計算ミス。
・公式を誤って理解していた。
・指定語句抜け。
などなど、その内容は様々です。

この分析が出来ていないと、成績向上のための学習計画を立てることが出来なくなります。
間違いのパターンの分析は「非常に重要なことである」ということを強く認識してください!
2.相対的な立ち位置を知ろう
こちらは1点目の『現状の学力を知る』という事に比べると、全く意識して来なかったという方が多いように思えます。

このような疑問を抱くかもしれません。
しかし、現状の学力を知ることと同様に『相対的な立ち位置を知る』ことは重要です。
なぜなら、鹿児島県立高校入試において合格ラインは絶対的なものではなく、その年の受験者の学力によって大きく左右されるものだからです。
たとえば令和2年度の鶴丸高校の合格ラインは約360点でしたが、令和3年度は約370点でした。
甲南高校の合格ラインは令和2年度が約340点。令和3年度は約360点でした。
「令和2年度に比べて、令和3年度の方が問題が易しかった」と言えるかとは思いますが、鶴丸高校の合格ラインが10点しか上がらなかったのに対して、甲南高校は20点も合格ラインが上がっています。
これは「前年であれば鶴丸高校を受験していたであろう学力層の一部が甲南高校を受験したため」と見ることが出来ます。
このように、鹿児島県立高校入試の各高校の合格ラインは年によって上下します。
したがって、

といったように、絶対的な点数だけで判断するのは非常に危険であるといえます。


偏差値は点数とは異なり、「受験者全体の平均点」や「受験者全体の得点のバラつき」が考慮された数値です。
そのため、数学が70点で英語が50点だったとしても、
得点は英語の方がかなり悪いのに、偏差値を比べると数学の方が悪い!

ということがあり得るのです。
※偏差値の求め方について解説をすると、やや長くなってしまうので、ここではざっくりと「平均点だったら偏差値50」で「平均点より上になればなるほど値が大きく」なり、「平均点より低ければ低いほど値が小さくなる」とお考え下さい。
以上のことから、模試においては点数に一喜一憂するのではなく、自分の相対的な立ち位置を把握することが重要であり、そのためには点数よりも偏差値に注目することが大切であるといえるでしょう。
まとめ
・間違いの分析が出来ていないと成績向上のための学習計画が立案できない。
・受験を意識して、点数ではなく偏差値で判断すべし!

「何をすればいいのか分からない!」とお困りの方は、お気軽にお問い合わせください^^
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。